札沼(さっしょう)線とは、國鐵時代、札幌から留萌本線の石狩沼田まで結んでいた路線。札幌と沼田、それぞれの頭文字を取り、「札沼」。
ところが・・・1972(昭和47)年に新十津川から石狩沼田間を早くも廃線。当時の北海道は網の目のように張り巡らしており、早くも廃線に追いやられる理由はよくわかりませんが・・・新十津川駅から少し離れた場所に函館本線の滝川駅があります。深川から留萌本線も出ているし、並行するようなレールは不要だったかも知れません。(私の憶測)
札沼線と名乗るのに実情にそぐわないのか、沿線に「あいの里教育大学」や「北海道医療大学」があることから、「都市学園線」という愛称が付けられました。
もともと非電化区間でしたが、札幌都市圏のベッドタウン化がすすみ、利用者も急増。輸送密度がとても高い、北海道医療大学駅までは電化。非電化区間に入ると、極端に少なくなり、浦臼までは1日7本。さらに終点の新十津川までなら3本っ!!1日わずか3本だけだと、たどり着くのにハードルの高い駅。
![]()
札幌からここまで都会的な風景が続くため、あんまり写真は撮らず。9月5日は土曜日なのに、車内を見回すと、席がほとんど埋まるほど学生がたくさん。補習か部活の生徒さんでしょう。先輩らしき人が乗ってきて、「はいっ!どうぞ!」という光景を見て、「これが北海道ルール?」「東京では先輩が乗ってきても知らんぷりだけど?」と友人とボソッ。
優先席のシートもチェックしてみたところ、そこに座る人は皆無。北海道ではどんなに満席でも健常者が優先席に座らないルールがあると聞いたとおりでした。
この写真を見て、気付きました。隣の駅は「石狩太美(いしかりふとみ)」駅。千葉県の房総半島、内房線にも「太海(ふとみ)」駅あり。太りたくない人がこの駅名を見るとどうも嫌味っぽい。手話表現は「太る」+「美しい」で「ふとみ」になるし、太海も「太い」+「うみ」。
![]()
新十津川行の始発、7時45分発。次は11時15分、その次は17時27分が最終。
![]()
キハ40 401。
![]()
わざわざサボを入れ替えなくてもよいように「学園都市線 COLLEGE TOWN(カレッジタウン)=大学の町?」表示。
![]()
昭和55(1980)年製造。車歴35年目。平成8(1996)年に苗穂工場で改造。
![]()
昭和の車両なので、スイッチボタンがたくさんありすぎて、よくわからない。まるで飛行機のコックピット。
![]()
さっきまでは都会的な風景、近代的なホームや駅舎ばかり続いていたのに、非電化区間に入ったとたん、この光景。
![]()
本中小屋(もとなかごや)駅でした。北海道は貨物列車の最後尾を連結していた車掌車を駅舎にしているところが多いです。
![]()
中小屋駅。
![]()
知来乙(ちらいおつ)駅。「乙」の字を見て父から聞いた話を思い出しました。「戦時中の成績は「甲乙丙(こう、おつ、へい)」。「甲」は極めて優秀、「乙」は普通。「丙」は悪いの3段階。戦後しばらくすると「優、良、可」といったように表示が変わった」とか。
![]()
交換設備を持つ、石狩月形駅に8時17分到着。発車時刻は8時40分。20分以上もあります。そこで途中下車。
ところが・・・1972(昭和47)年に新十津川から石狩沼田間を早くも廃線。当時の北海道は網の目のように張り巡らしており、早くも廃線に追いやられる理由はよくわかりませんが・・・新十津川駅から少し離れた場所に函館本線の滝川駅があります。深川から留萌本線も出ているし、並行するようなレールは不要だったかも知れません。(私の憶測)
札沼線と名乗るのに実情にそぐわないのか、沿線に「あいの里教育大学」や「北海道医療大学」があることから、「都市学園線」という愛称が付けられました。
もともと非電化区間でしたが、札幌都市圏のベッドタウン化がすすみ、利用者も急増。輸送密度がとても高い、北海道医療大学駅までは電化。非電化区間に入ると、極端に少なくなり、浦臼までは1日7本。さらに終点の新十津川までなら3本っ!!1日わずか3本だけだと、たどり着くのにハードルの高い駅。

札幌からここまで都会的な風景が続くため、あんまり写真は撮らず。9月5日は土曜日なのに、車内を見回すと、席がほとんど埋まるほど学生がたくさん。補習か部活の生徒さんでしょう。先輩らしき人が乗ってきて、「はいっ!どうぞ!」という光景を見て、「これが北海道ルール?」「東京では先輩が乗ってきても知らんぷりだけど?」と友人とボソッ。
優先席のシートもチェックしてみたところ、そこに座る人は皆無。北海道ではどんなに満席でも健常者が優先席に座らないルールがあると聞いたとおりでした。
この写真を見て、気付きました。隣の駅は「石狩太美(いしかりふとみ)」駅。千葉県の房総半島、内房線にも「太海(ふとみ)」駅あり。太りたくない人がこの駅名を見るとどうも嫌味っぽい。手話表現は「太る」+「美しい」で「ふとみ」になるし、太海も「太い」+「うみ」。

新十津川行の始発、7時45分発。次は11時15分、その次は17時27分が最終。
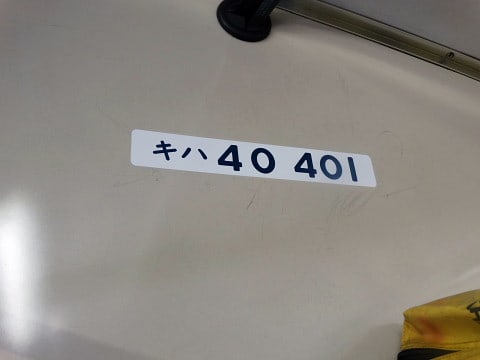
キハ40 401。

わざわざサボを入れ替えなくてもよいように「学園都市線 COLLEGE TOWN(カレッジタウン)=大学の町?」表示。

昭和55(1980)年製造。車歴35年目。平成8(1996)年に苗穂工場で改造。

昭和の車両なので、スイッチボタンがたくさんありすぎて、よくわからない。まるで飛行機のコックピット。

さっきまでは都会的な風景、近代的なホームや駅舎ばかり続いていたのに、非電化区間に入ったとたん、この光景。

本中小屋(もとなかごや)駅でした。北海道は貨物列車の最後尾を連結していた車掌車を駅舎にしているところが多いです。

中小屋駅。

知来乙(ちらいおつ)駅。「乙」の字を見て父から聞いた話を思い出しました。「戦時中の成績は「甲乙丙(こう、おつ、へい)」。「甲」は極めて優秀、「乙」は普通。「丙」は悪いの3段階。戦後しばらくすると「優、良、可」といったように表示が変わった」とか。

交換設備を持つ、石狩月形駅に8時17分到着。発車時刻は8時40分。20分以上もあります。そこで途中下車。